
ということで…こんにちは!鈴風カオリです。
今回はストレスについて、
心理学専攻で大学卒業後 現在も独学で心理学を学び続けている私が
お話していきます!

こんにちは!KIRAです。
人間が切っても切れない関係…ストレス!
そもそも何でストレスかかっちゃうんだろ?

原因はいろいろあるからこの記事で解説していくね!
後、ストレスのサインと解消方法についてもお話していくので、
そもそもストレスを抱えてることに気づきづらい人、
解消方法が知りたい人にもぜひ聞いてほしい内容です〜!

いいね!教えてー❤️

は〜い!
ではでは!早速今回の内容を紹介するね!
今回は自分の抱えるストレスと向きあって
今以上にHappyな毎日を過ごしたい人に向けてお話ししていきます。
この記事を読むことで普段気づかなかったストレスを溜め込んでしまう理由が
分かるかもしれません。
ストレスと上手く付き合うには、まずはストレスについて知ることから始まります!
ぜひ最後まで読んでいってくださいね!
1.ストレスを溜め込む心理について

まず初めに、ストレスを溜め込む心理について解説します。
ストレスというのは知らず知らずのうちに私たちの心や体に溜まっていくので、
気づかないまま我慢を続けているといつの間にか疲れ果ててしまうこともあるかもしれません。
何故人はストレスを溜め込んでしまうのでしょうか?
理由は大きく分けて以下の5つが考えられます。
・感情を抑え込む癖がある(気遣い過多)
・完璧主義や高い自己欲求がある
・適切な休息不足
・過剰な情報量への疲労
・自分でコントロールできない状況(環境の変化への不適応)
早速、それぞれ解説していきます。
1-1.感情を抑え込む癖がある(気遣い過多)
ストレスを溜め込む心理の中でも
感情を抑え込む癖がある(気遣い過多)というのが有力だという話をします。
何故なら、この癖を持つ人は、相手に嫌な思いをさせたくない、
場の空気を悪くしたくないといった気持ちが強いから。
その結果、自分の感情を後回しにして心の中に不満や辛さをため込んでしまいがち。
感情を抑え込む癖は、心理学的に自己犠牲の傾向と深く結びついています。
この癖が強い人は、他人を優先しすぎて自分の感情に気づきにくくなることがあります。
また感情を表現する機会が少ないため、ストレスを発散するタイミングも逃しやすいんです。
これが蓄積型のストレスとなって結果的に心の負担を大きくしてしまうんですね。

仕事に関しては特に感情を抑えるのが悪いわけではなくない?
仕事に感情を持ち込むべきじゃない!って考えもあると思うんだけど…?

そうだね!
私もどちらかといえば「仕事に感情を持ち込まない派」なんだけど、
私の場合は感情を持ち込まずにできるっていうのは、
最初は嫌なことだったとしてもポジティブな考えにシフトできるってことだと思うんだよね。

ほうほう。

例えば苦手意識のある仕事を頼まれたとき、
最初は「時間かかるだろうな…ちょっと憂鬱だな」って思ったとしても、
「でもやり方を工夫すれば克服できるかもしれない!チャレンジしてみよう!」とか、
「先に苦手だということを先方に伝えた方が気楽だな」と思えば、それが可能であれば実行したりして前向きな気持ちになれるように努めてみるの。
でもこれって状況や人によっては難しい場合もある。

なるほどー。
それが「我慢しすぎ」や「無理をしている」状態に繋がって、
心身に負担を与えちゃうのね。

そういうこと!
大切なのは感情を押し殺すことではなく、
自分の感情を大切にしつつも相手を尊重する方法を見つけること。
嫌なことを断りたい場合は「ごめんなさい、今は難しいです」と誠実に伝えれば、
相手に嫌な印象を与えずに自分の意思が伝わるはずだよ!
1-2.完璧主義や高い自己欲求がある
完璧主義や高い自己欲求を持つことが
ストレスの原因になっているのではないかという話をします。
何故なら、完璧主義者は自分に対して常に高い基準を求める傾向があり、
ミスを極端に嫌って「自分はもっとできるはず」というプレッシャーを自らに課すから。
その結果、目標が達成できなかったり期待通りに進まなかった時、
自分を責める気持ちが強まりストレスを抱えやすいんです。
またこのような心理状態では、周囲のサポートやアドバイスを受け入れづらくなり、
結果的に孤立しやすくなります。
他人の評価を過剰に気にするため心の余裕が失われて、ストレスの大きな要因に繋がります。

私自身、配信視聴者さんにバレるほどの完璧主義者なので
自分のことを話してて胸が痛いんだけども…(笑)
これが原因で鬱気味になったこともあるので皆にも気をつけてほしい!

ええ!そうだったんだ!
でも完璧主義って悪いものでもないよね?
高い基準を持つことが成長や成功に繋がるんじゃない?

うんうん!
確かに完璧主義や高い自己欲求がある人は、
結果的に素晴らしい成果を出すことも多いね。
でもその過程で自分を追い詰めすぎてしまうと心身のバランスを崩しちゃう。
私は完璧主義の自分を受け入れて、自分の本当の力量も受け入れて、
完璧の定義を変えることで心身楽になったよ!

完璧の定義?

うん。
ずっと「一人で何もかも完璧にできる人」になりたいって無意識に思ってたみたいなんだけど、
そんな神様にしか成せないようなこと望んでたら苦しいだけって気づいたの。
だから全てを完璧にするんじゃなくて、今は「優先順位をつけて物事によって精度を変えることができる」っていうことを美徳にしてるよ。

ほうほう。
例えば「ここだけは完璧を目指すけれど、他の部分は60%の力で大丈夫」みたいな?

そう!
あとは自分一人で全てを背負う必要はないと考えることも重要。
周囲のサポートを受け入れることで心に余裕が生まれて、
ストレスも大幅に減らせるよ!
完璧主義を「良い方向」に活かすには、
自分の限界を認めつつ柔軟な視点を持つことが鍵。
1-3.適切な休息不足
適切な休息不足がストレスの原因になっているのではないかという話をします。
何故なら休息は、ストレスを解消して心身をリセットするために欠かせないから。
実際にこんな研究結果があるようです。
それにも関わらず、忙しい日々を送る中で「休む時間がもったいない」と感じたり、
「休むのは甘え」と思い込んでしまう人もいますよね。
そんな状態が続くと、心と体に知らず知らずのうちに負担をかけてしまうんです。
休むべきタイミングで休めないと、体が緊張状態から抜け出せずイライラや不安感が蓄積していきます。
さらに、疲労が溜まった状態では冷静な判断ができなくなり、
人間関係や仕事において余計なトラブルを招くことも。
例えば家事や育児を一人で抱え込む親が「家族のために頑張らなきゃ」と無理を続けるケース。
こうした状況では、「イライラして怒りっぽくなった」と自覚した時には
すでに限界を迎えていることが少なくありません。

こんにちは!Asahiです!
私も実際に「家事や育児」をしている身だから分かるんだけど、
そもそも休息を取る余裕がないんだよね…

確かにすべての人が自由に休息を取れるわけではないよね。
でもストレスを抱え続けてしまうと長期的にはパフォーマンスが低下して悪循環。
忙しいのは百も承知で、それでも少しずつ「休息の質」を高める工夫が必要です…!

「休息の質」を高める工夫?

「休息」については後で紹介する「3.ストレス解消方法について」のことなので詳しくは後で読んでみてほしいんだけど…
例えば解消方法の一つに「深呼吸する」っていうのがあるの。
深呼吸は深呼吸でも回数を熟すより、
1回の息を吸って息を吐く動作を丁寧に質の良いものにした方が効果はあるし、
結果的に時間も短縮にもなる。

なるほど!

あとは「全てを一人でやらなければいけない」という思い込みがあるのならそれは捨てて、
周りに頼ることも大切。
家族や同僚と役割を分担したり必要に応じて専門家に相談することで、
心の余裕を作ることができるよ!

うんうん!
サポート大切!

あとXの投稿にも書いたんだけど…
もし可能であれば「タスク」と同時並行で「自由な時間があればやりたいこと」をやるといいよ!
私も「ご飯を食べる」っていうタスクを熟しながら「観たい映画を観る」っていうやりたいことに取り組んだりしてる!
最近は忙しい一日の中に如何にして休息を取り入れるかっていうことを常に考えてるな〜。
適切な休息を確保するのは自己管理の一環でもあります。
そのため、まずは休むことは甘えではなく次のための準備と前向きに捉える視点が必要なんです。
1-4.過剰な情報量への疲労
過剰な情報量への疲労がストレスの原因になっているのではないかという話をします。
何故なら、人間の脳は限られた情報量しか処理できない仕組みになっているにも関わらず、
現代では必要以上の情報を無理に処理しようとする場面が多いから。
スマホやパソコンから流れ込むニュースや通知、SNSの投稿など、次から次へと情報が飛び込んでくる環境にいると、
脳が疲労して集中力が落ちたり無意識にプレッシャーを感じてしまうことがあります。
さらに、SNSやインターネットで他人の成功や意見に触れることで、
「自分はどうすればいいんだろう」と悩みや不安を増幅させることも少なくありません。

情報を取捨選択すれば問題ない?

それも負担を軽減できる良い考えだね!
でも「選択する」という行為そのものがエネルギーを消費しちゃうから、
もっとおすすめなのは、情報を完全に遮断する時間を作ること。
例えば、1日のうち決まった時間だけスマホを見ないルールを設けたり、
週に一度SNSやニュースから離れる「デジタルデトックス」を試すとか…。
詳細は後の「スマホや情報から距離を置く」で解説するね!

はーい❤️
1-5.自分でコントロールできない状況(環境の変化への不適応)
自分でコントロールできない状況がストレスの原因なんじゃないかという話をします。
何故なら、人は急激な環境の変化に適応できないと感じるとき、
無意識のうちに強い不安やストレスを感じやすくなるから。
人間というのは自分で状況をコントロールできると安心感を得られる生き物なので、
自分の意思とは関係なく状況が動いてしまうと脳がその変化を処理しきれなくなることがあるんです。
その結果、身体や心に負担がかかりストレスが蓄積してしまう。
特に、自分の行動が結果に繋がらないと感じるとやる気や希望も削がれてしまうことがあります。
ここで具体例を挙げます。
・職場の急な異動や仕事内容の変更
新しい環境で仕事を覚えながら人間関係も築く必要があると心の負担が一気に増えますよね。
さらに、自分の希望ではなく会社側の都合で異動が決まった場合「どうして私が?」と無力感を抱くことも。
・受験生や転校生など
新しい学校や地域に馴染もうとする中で、
自分の努力だけでは解決できない問題(周囲の反応や文化の違い)があると
適応するのが難しく感じられることもあります。

こんにちは!最近引っ越したサポタです!
環境の変化は成長の機会で、
それを乗り越えることで人は強くなるという考えもあるよね?

確かに環境の変化を乗り越えることで成長する側面もあります!
でも、それが効果を発揮するのはある程度コントロール感を持てる場合や、
サポートがある場合。
完全に自分の力だけではどうにもならない状況に置かれると、
成長どころか、むしろ精神的な消耗が進んでしまうかも…。

そうか…。
個人の努力だけでは解決が難しいとなると
「変化を楽しむ余裕」よりも「現状を乗り越えるストレス」が優先されてしまうかもしれないなー。

うん!
だからこそ、環境の変化に対処するには
自分が少しでもコントロールできる部分を見つけたり、
周囲からのサポートを得ることが重要。
例えば、相談できる相手を作るだけでも心が軽くなる場合があるよ。

なるほど!

結局のところ、変化が成長につながるかどうかは
その人が感じるコントロール感の有無が鍵ということだね!
2.ストレスの心理的・行動的サインについて

次に、ストレスの心理的・行動的サインについて解説していきます。
ストレスが溜まると、私たちの心や体にはさまざまなサインが現れるものですが、
その変化に気づかないまま過ごしていると
後になって「なんでこんなに疲れてるんだろう?」と戸惑ってしまうこともあるでしょう。
ではどういったサインがあるのかということですが、
以下の6つが考えられます。
・睡眠の乱れ
・食欲の変化
・イライラや怒りっぽさ
・集中力や記憶力低下
・身体的な不調
・対人関係の回避
既に「これ、自分にも当てはまるかも?」と思うものがあるかもしれませんね。
それでは一つづつ解説していきます。
睡眠の乱れ
睡眠の乱れというのは、ストレスが心や体に影響を与えているサインの一つ。
何故なら、ストレスを感じると脳が過剰に活動してしまいリラックスするための時間が十分に取れなくなるから。
さらに十分な睡眠が取れないと、翌日のパフォーマンスが低下したりイライラしやすくなったりしてしまい、
また新たなストレスを生むという悪循環になってしまうことも少なくありません。
以下のような状況の人はこれに当てはまるかもしれません。
・仕事の締め切りが迫っていて、頭の中でずっと考えごとをしてしまい、気づいたら朝。
・新しい環境に慣れなくて、寝る前にあれこれ思い悩む。
・日中にスマホをずっと見ていて、寝る直前まで画面を眺めてしまう。
食欲の変化
食欲の変化というのは、ストレスが体や心に影響を及ぼしているサインの一つです。
何故なら、ストレスを感じた時に分泌されるホルモンが
食欲を刺激したり抑えたりする働きを持っているから。
以下のような状況の人はこれに当てはまるかもしれません。
・忙しい時期が続いて、気づいたらお菓子ばかり食べている。
・試験やプレゼンの直前で緊張しすぎて何も喉を通らない。
・ストレス解消のために、深夜にドカ食いしてしまう癖がついた。
食欲の変化は短期間で終わることもあれば長期的に続いて健康に影響を及ぼすケースもあります。
イライラや怒りっぽさ
イライラや怒りっぽさというのは、ストレスが引き起こす心理的・行動的サインとして有力です。
何故なら、ストレスを感じると脳が闘争・逃走反応と呼ばれる防御的なモードに入るから。
この時 心や体が緊張状態になり感情をコントロールする余裕がなくなってしまうことがよくあります。
結果として、普段なら気にならないような些細なことでも
強いイライラや怒りを感じやすくなるんです。
以下のような状況の人はこれにあてはまるかもしれません。
・家庭内で、子供やパートナーの些細なミスに耐えられなくなる。
・渋滞や電車の遅延で、過剰にストレスを感じてしまう。
集中力や記憶力の低下
ストレスがかかると集中力や記憶力の低下が見られることがあり、
心理的・行動的なサインの一つとして有力です。
何故なら、ストレスを受けると脳が過剰な情報やプレッシャーにさらされ、
脳が疲労し正常な機能が妨げられることがあります。
この状態は脳疲労とも呼ばれ、認知機能の低下を引き起こします。
脳疲労とは、過剰な情報やストレスを受けることにより脳が正常に機能しなくなった状態(例えば、認知機能が一時的に低下した状態など)のこと。認知機能が低下すると、ミスの増加や情報処理のスピード、正確性の低下などのいろいろな悪影響が起こります。
出典:アリナミン「あなたの物忘れは脳疲労が原因?認知症や加齢による物忘れとの違いや対処法を解説」
以下のような状況の人はこれに当てはまるかもしれません。
• 会議中に話の内容が頭に入らず、重要なポイントを見逃してしまう。
• 日常的なタスクの手順を忘れてしまい、ミスが増える。
• 人の名前や約束の時間を思い出せず、混乱する。
身体的な不調
ストレスがたまると身体的な不調が現れることがあり、
心理的・行動的サインとしても非常に有力なものです。
何故なら、ストレスが強いと体内でコルチゾールというストレスホルモンが過剰に分泌されるから。
このホルモンは短期的には危機的状況への対応を助ける役割がありますが、
長期的に分泌が続くと身体に悪影響を及ぼします。
例えば、免疫力が低下して風邪をひきやすくなったり、
胃酸の分泌が増えて胃痛や胃もたれを引き起こす等。
また 自律神経の乱れにより、肩こりや頭痛、睡眠障害といった症状も出やすくなります。
仕事の締め切りに追われた時なんかにそのような体の変化を感じた場合は、
ストレスによって体が悲鳴を上げているサインです。
対人関係の回避
対人関係の回避というのはストレスの心理的・行動的サインとして有力です。
何故なら、ストレスがかかると、人は自分を守るためにエネルギーを節約しようとするから。
その結果 他人と関わること自体が負担に感じられ、対人関係を避けるようになるのです。
例えばこんな行動が頻繁に見られることがあります。
• 飲み会や集まりの誘いを断りがちになる。
• 電話やメッセージが来ても「後でいいや」と思って放置してしまう。
• 何かと理由をつけて一人になれる時間を増やそうとする。

対人関係を避けるのは、ただの性格や気分の問題って場合もあるよね?
原因が「ストレスによる対人関係の回避」と「性格や気分」、どっちなのか見極める方法はあるの?

うん!あるよ!
まず、性格や気分による回避は長期間にわたることが少なくて
特定の状況だけに限定されることが多いの。
一方で、ストレスによる回避は普段は気にならない人間関係や日常のコミュニケーションまで「面倒だ」「重い」と感じてしまうのが特徴。

なるほど!

さらに ストレスが原因の場合は、回避に加えて他のストレス症状
…例えば、疲労感や睡眠不足も一緒に現れることが多いよ!

そっかー!
対人関係を避けつつ、「なんでこんなに疲れてるんだろう?」って思う的な?

そう!そんな感じ!
3.ストレス解消方法について

最後にストレス解消方法について解説していきます。
今回ご紹介するのは以下の7つ。
・適度な運動をする
・深呼吸や瞑想を取り入れる
・趣味や好きなことに没頭する
・自然に触れる
・新しいことに挑戦する
・スマホや情報から距離を置く
・動物やぬいぐるみで癒される
それぞれの方法を詳しく解説していくので、
ポイントは、自分に合った方法を見つけて無理なく続けてみてください。
適度な運動をする
ストレス解消法の中でも、適度な運動をするというのは非常に有力な方法の一つです。
ストレスを感じると体内ではコルチゾールというホルモンが増えますが、
運動をすることでこれを減らしやすくなるのです。
さらに、エンドルフィンといういわゆる幸せホルモンが分泌されるため、
気分がリフレッシュされる効果も期待できます。
例えば、以下のような運動がストレス解消に効果的と言われています。
• 軽いジョギングやウォーキング
• ヨガやストレッチ
• 自宅での軽い筋トレやエクササイズ
• ダンスやスポーツなど、楽しく体を動かす活動
深呼吸や瞑想を取り入れる
深呼吸や瞑想を取り入れるというのは有力なストレス発散方法の一つです。
深呼吸をすることで副交感神経が優位になり、心拍数や血圧が自然と落ち着き、
体の緊張がほぐれてストレス反応が和らぐのです。
さらに、瞑想は「今この瞬間」に集中する練習になるため、
過去の後悔や未来の不安から解放されやすくなります。
忙しい日常の中で1分だけも瞑想をすると、不思議と頭がスッキリすることもあります。
例えば、以下のような場面で活用できます。
• 緊張するプレゼンや試験前に深呼吸をする
• 朝の目覚めや寝る前に短時間の瞑想を取り入れる
• 感情的になりそうなときに一旦呼吸を整える
深呼吸や瞑想は、一回の実践だけで劇的にストレスが解消するわけではありません。
続けていくことで、ストレスに対する耐性が少しずつ高まることが研究で明らかになっています。
趣味や好きなことに没頭する
趣味や好きなことに没頭するというのは、有力なストレス解消方法の一つです。
何故なら、その瞬間だけでもストレスの原因を忘れることができるから。
好きなことをしている間に分泌されるドーパミンやエンドルフィンといった脳内物質は、
気分を高める効果があります。
没頭する時間を継続的に作ると、ストレス解消だけでなく前向きな気持ちを取り戻すことにもつながるんです。
例えば…
• 絵を描くことが好きな人なら、キャンバスに向かう時間が心の癒しに。
• 料理が好きな人なら新しいレシピに挑戦することで、創造的な時間を過ごせます。
• 趣味がない場合は小さなことから試してみると良いです。
「一度もやったことのないことに挑戦してみる」「気になる本や動画を参考にする」等。
また、時間がない人は1日5分だけでも好きなことをする時間を作る工夫がおすすめ。
スマホを置いて5分だけ絵を描く、短い動画を見てみるなど、短時間でも効果は期待できます。
自然に触れる
自然に触れるというのは、とても効果的なストレス発散方法の一つです。
例えば、森林浴をすると、木々の香りや風の音が心を落ち着けてくれることがありますよね。
これは自然が持つ「癒やしの力」が、私たちのストレスホルモンを低下させると言われているからです。
さらに、太陽の光を浴びるとセロトニンという幸福ホルモンが分泌されるため、
気分が明るくなる効果も期待できます。
「外出面倒…」と思う人には以下の方法がおすすめ。
• わざわざ遠出しなくても、近所の公園でベンチに座るだけでもOK。
• 自然に触れる時間が短くても、例えば昼休みに外で10分だけ散歩をするだけでも
気分転換には十分です。
• 「家でリラックスしたい」という場合でも、
観葉植物を部屋に置いたり自然音の動画やアプリを活用することで、
ある程度自然の癒やしを取り入れることができます。
新しいことに挑戦する
新しいことに挑戦するというのは、とても有力なストレス解消方法の一つです。
挑戦することで脳が活性化してマンネリ化した日常から抜け出せます。
また、「できた」という達成感や、「これなら私もできるかも」という自信がつくことが
ストレスの軽減につながるんです。
特に挑戦すること自体が新鮮な刺激になり、
ストレスの原因となる固定観念やルーティンから解放されるのも大きなメリットだと言えます。
さらに、挑戦を通して新しい趣味や仲間ができることもあり、
これがストレスを感じにくい環境作りに役立つ場合もあります。
例えば…
• 料理をほとんどしない人が新しいレシピに挑戦してみると、
「意外と楽しい!」と感じることがあるかも。
さらに、成功した料理を家族や友人にふるまえば、
そこから会話が生まれて気持ちが明るくなったりします。
• 運動不足の人がヨガやランニングに挑戦してみると、
最初は難しくても体が軽くなって達成感を得られるかもしれません。
• ボランティア活動や新しい勉強を始めてみることで、
これまで知らなかった世界が広がり日常の中に新しい楽しみが見つかることもあります。
新しいことへの挑戦は、小さいことから始めれば不安を軽減できます。
例えば、「英会話を学びたいけど不安」という人は、
いきなり教室に通うのではなくアプリを使って一日5分だけ試してみるのも◎。
また、「失敗したらどうしよう」と考えるよりも、
結果より過程を楽しむことを意識してみてください。
挑戦自体が新しい経験として自分の糧になるので、
たとえ結果が思い通りでなくても少しずつ前向きになれるはずです。
私もこの前初めての試みをしてみました!
スマホや情報から距離を置く
スマホや情報から距離を置くというのは、ストレス解消に有力な選択肢だと思います。
私たちは日常的にスマホやインターネットを通じて膨大な情報に触れていますが、
それが逆に脳や心を疲れさせる原因になっていることが多いんです。
特に、SNSの情報やニュースを見ていると、
必要以上に刺激を受けたり比較してしまったりしてストレスを感じやすくなることも。
スマホを置いて情報から少し離れるだけで、頭がスッキリする感覚を味わえると同時に、
自然と自分の時間が増えて気持ちの余裕ができるのも良いところ。
例えばこんな方法がおすすめ。
• 休日の朝にスマホを見ずに散歩や読書からスタートしてみる。
起きてから5分間だけでも良いです。
それだけでも、普段とは違う落ち着きを感じられるかもしれません。
• 寝る1時間前にスマホを触らない時間を作る。
画面の光と刺激的な情報を避けることで、リラックスできて睡眠の質も向上します。
• 旅行に出かけた際は、あえてスマホを使わずに過ごす。
その場の景色や空気をもっと楽しめます。
「今の時代、スマホや情報がないと生活が成り立たない」、
「暇になってしまって逆にストレスがたまる」という声もあるかもしれませんが、
スマホから距離を置く時間を限定的にするだけでも効果があります。
生活全体でなく、特定の時間帯だけスマホを使わない「ルール」を作るといいかもしれません。
動物やぬいぐるみで癒される
動物やぬいぐるみで癒されるというのは、ストレス解消に有力な手段だと思います。
まず、動物は言葉を持たない分、その仕草や存在自体が純粋で癒しを与えてくれます。
一方、ぬいぐるみはリアルな動物に比べて手軽で扱いやすく、
自分のペースで癒しを感じられるアイテム。
触れるだけでストレスホルモンが減少したり、心拍が落ち着く効果があると言われています。
動物が飼えない環境でも、動物の動画を観たり動物カフェや動物園に行ったり、
ふわふわのぬいぐるみを持っておくことならできるという人多いんじゃないでしょうか?
ぬいぐるみでのストレス発散については、
詳しくは以下の投稿で解説しているので良ければチェックしてみてください!
4.まとめ

今回はストレスについてまとめてみたんだけど
どうだったかな?

Happyな毎日を過ごすためにも
ストレスのことをもっと知るべきなんだなって思った!

うんうん!
ストレスは辛い出来事はもちろん、楽しい出来事が起きてもかかるものだから、
ぜひ今回の内容を参考にストレスと向き合ってみてね!
じゃあ最後に内容を振り返ってみよ〜!
・ストレスを溜め込む心理には「感情の抑え込身」「完璧主義」「休息不足」
「情報量への疲労」「コントロール不足」等がある。
・原因がストレスである時と他にある場合との違いを見極める必要がある。
・ストレスから来る症状なのかを見極めるには、
ストレス以外の原因がある場合と比較したり、サインが複数発生しているかどうか確認するように。
・ストレス解消方法は様々あるが、自分に合ったものを見つけて取り入れましょう。
無理なく小さなことから始めてみるのをおすすめします。
・発散方法を試しても症状が長引く場合は、専門家に相談することも検討しましょう。
今回はストレスが溜まる原因、サイン、解消方法についてまとめてみました。
SNSでも心理学に関する内容や前向きな考え方等について公開しています。
フォロー等していただけると今後の活動の励みになりますので、
もし宜しければお願いいたします…!
各SNS(TikTok、X、Instagram)
REALITY(配信アプリ)

最後まで読んでいただきありがとうございました!
あなたに幸あれ!
またねです〜!



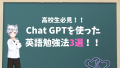

コメント