
ということで…こんにちは!鈴風カオリです。
今回は思い込みの心理について、
心理学専攻で大学卒業後 現在も独学で心理学を学び続けている私が
お話していきます!

こんにちは!KIRAです。
思い込みが行動や判断に繋がって、
それによって人間関係とか仕事・人生にも影響してるって思うと
ちょっと怖いかも!
でも実際にどういう時に思い込みが発生しているかは
自分じゃ気づきにくいものだよねー。

うんうん!
それ気づくためにはまず思い込みが起こる人間の心理を知っておく必要があるの。
思い込みを克服してオープンな考え方を持つ方法についても
私なりにまとめているのでぜひ今回の内容を参考にしてみてね!

おおー!気になる!
教えてー❤️
今回は人間関係や仕事・人生を今以上に良好にさせたい人に向けて、
人間であれば誰でもあり得る思い込みについてお話ししていきます。
この記事を読むことで普段の自分の考えや捉え方を見直す大切さを知り、
それを実践することで今まで思うようにいかなかったことも、
「案外すんなりとできた!」という体験に繋がるかもしれません。
ぜひ最後まで読んでいってくださいね!
1.思い込みが起こる人間の心理
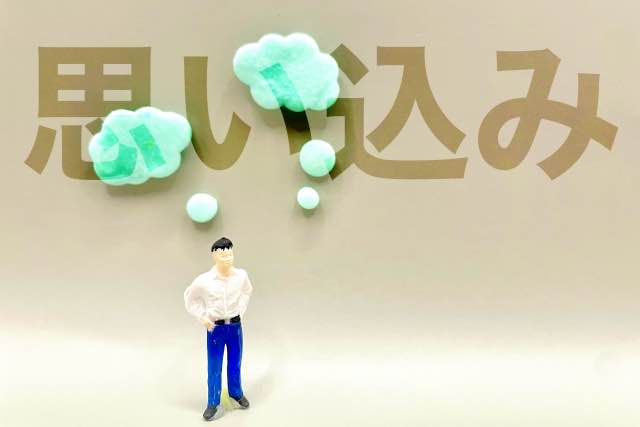
思い込みというのは、無意識のうちに私たちの行動や考え方に影響を与えているもの。
ではそもそも、なぜ思い込みというものが発生するのでしょうか?
結論、大きく分けて以下の5つが影響していると考えています。
・ステレオタイプによる思い込み
・バイアスによる思い込み
・防衛機制による思い込み
・選択的注意による思い込み
・社会的影響による思い込み
それぞれ順番に解説していくので、
自分の思い込みに気づくきっかけにしてみてください!
1-1.ステレオタイプによる思い込み
まず初めに、思い込みが起こる人間の心理について、
ステレオタイプが有力だというお話をします。
ステレオタイプというのは、
特定の集団や個人に対して過去の経験や社会的な影響から
固定的なイメージを持つことです。
人間はたくさんの情報を効率よく処理するために物事をまとめて捉える傾向があるので、
知らない人や状況について判断するときにステレオタイプが思い込みとして働くんですよね。
例えば、「年配の人はデジタルに弱い」というステレオタイプを持っているとしましょう。
そのイメージが強いと、年配の方がスマホを使っている場面でも
「操作が分かってないんじゃないか」と勝手に決めつけてしまうかもしれません。
その結果、誤ったサポートや不要なアドバイスをしてしまって
失礼に感じられるかも…。
こうしてステレオタイプが私たちの判断や行動に影響を与え、
実際とは異なる認識をしてしまう原因になるのです。

ステレオタイプは実際の経験やデータに基づいているんだよね?
それを使うのは効率的だと思うんだけど…?

うん、確かに全くステレオタイプを持たないでいることは難しいし
時には役に立つこともあるんだけど、
それに頼りすぎちゃうと その人の背景や個性を無視することになる。

なるほど。

例えば、ビジネスや国際関係においてであれば相手国の文化や価値観を知っておくことは大事だと思う。
でも「○○人だから」「障がい者だから」「男性だから」みたいに
集団全体に当てはまるイメージを使って個々を判断するのは危険だね。

そっかー!
ちなみに、私は逆に「ステレオタイプで見られてるな〜」ってことを度々経験しています。
例えば中学生時代。
その頃は目立ちたくなくて透明人間になりたいくらいだったので学校では地味な髪型にしていました。
しばらくして視力が悪くなってきたのでメガネもかけました。
すると周りからは「カオリちゃん頭良さそう」って言われるようになったんです。
実際は全く勉強できなくて赤点ばっかりだったのに…
その事実を知っているのは先生と親のみだったんです。
いやぁ…ステレオタイプってこわい…。(笑)
1-2.バイアスによる思い込み
次は思い込みが起こる人間の心理について、バイアスが特に有力だというお話をします。
バイアスというのは、ある特定の方向に偏った判断や無意識に取ってしまう思考の傾向のこと。
先入観・偏見ともいわれています。
人間はすべての情報を完全に公正に扱うのが難しいので、
経験や環境に基づいた思考の癖が影響してくるのです。
その結果、知らないうちに特定のパターンで物事を判断するようになると
それが思い込みに繋がるんですね。
ここで前でお話しているステレオタイプとの違いを見ておきましょう。
ステレオタイプは、一人ひとりが持つ特定のイメージで、それが当たり前だと思っており、自分が持つステレオタイプを意識する機会はあまりありません。
出典:XICA「サイカロン」ステレオタイプとは
一方のバイアスは、ステレオタイプに何らかの評価や感情、態度、行動が加わったものです。
そんなバイアスにはいくつか種類があるのですが、
ここでは確証バイアスというものを例に挙げます。
確証バイアスは自分の信念を裏付ける情報だけを選び、反対の情報を無意識に無視する傾向のこと。
つまり、バランスの取れた判断ができなくなるということ。
「この商品は素晴らしい!」と思っていると良いレビューばかり探して読み、
悪いレビューは見ないようにしたり、軽視したりするといった感じ。
1-3.防衛機制による思い込み
次は思い込みが起こる人間の心理について、防衛機制が特に有力だというお話をします。
防衛機制というのは、人がストレスや不安に直面したときその感情から自分を守るために
無意識に働く心理的なメカニズムのこと。
この防衛機制が働くと自分に都合の良い解釈や思い込みが生まれて、
実際の状況や事実と異なる判断をしてしまうことがあるのです。
例えば合理化という防衛機制があるのはご存知ですか?
合理化は自分の行動や失敗を正当化するために理由をつけることをいうのですが、
例えば仕事でミスをしたときに
「自分が悪いんじゃなくて時間がなかったからだ」と
思い込んでしまうのもこれに当てはまります。
本当は準備不足が原因かもしれないのに、
そう考えることで自分を守ろうとするんですね。

でも防衛機制って悪いものではないんでしょ?

うん、防衛機能自体は自分を守ろうと働く機能だから
もちろん悪いものではないんだけど、
防衛機能によってそのまま思い込みを続けてしまうと本当の問題に向き合わず
成長の機会を逃してしまうことがあるので注意…!

なるほど!
ミスをすべて外部の要因にしてしまうと次に同じような状況が来たときに
同じ失敗を繰り返す可能性あるもんねー。
1-4.選択的注意による思い込み
思い込みが起こる人間の心理について、選択的注意が有力だというお話をします。
選択的注意というのは、たくさんの情報の中から自分が重要だと思うものだけを無意識に選び取ること。
人間の脳は常に膨大な情報にさらされていますが、
そのすべてを処理するのは難しいので、
自分が「これが大事」と思う部分だけを強調して捉えています。
例えば、賑やかなパーティで自分の名前が呼ばれた時に気づけるのもこの選択的注意のおかげなんです。
ですが全体の情報を正確に理解できないと偏った判断をする場合もるので注意が必要です。
1-5.社会的影響による思い込み
思い込みが起こる人間の心理について、社会的影響が特に有力だというお話をします。
社会的影響というのは、他人や社会から受ける影響が自分の考え方や行動に大きく関与すること。
周りの人の言動や態度に影響されて自分の意見や判断を変えることで、
思い込みを作り出す可能性があるのです。
例えばSNSで多くの人が「この映画は最高だ」と言っていると、
まだ観ていなくても「この映画は素晴らしいに違いない」と思い込むことがありませんか?
それは、他人の評価に影響されて自分も同じように感じるべきだと思い込む同調効果の一例です。
結果として自分の本当の感覚や考えとは異なる思い込みが形成されてしまうんですね。

社会的影響を受けることで情報を効率的に処理できるとかのメリットもあるけど、
その影響が過剰になって自分の意見や判断が曖昧になってる人も多そうだもんねー。

うんうん!
相手が正しい情報を発信してたら良いんだけど、
それが相手の思い込みだったとしたら…
情報収集するのは良いことだけど、
一つの意見を鵜呑みにしたりなんでも信じたりするのは良くないってことだね。

うんうん!
2.思い込みによる人間への影響

次は思い込みによる影響についてです。
思い込みというと思い込みなので意識しないと自分では気づけませんが、
私たちのその後に大きく影響する可能性もあります。
では、実際にどのような影響があるのかですが、
大きく以下の3つが挙げられます。
・行動や判断への思い込みによる心理的影響
・人間関係への思い込みによる影響
・仕事や人生への思い込みによる影響
では早速それぞれ解説していくので、
ご自分に当てはまるものがないか比べながら読んでみてくださいね!
2-1.行動や判断への思い込みによる心理的影響
思い込みが行動や判断に与える影響は、日常のちょっとした場面でも現れるものです。
例えば、スポーツや趣味の場面で自分の能力に対する思い込みが影響することも。
「自分はこのスポーツが苦手だ」とか「この技術は無理だ」と思い込んでしまうと、
その結果、挑戦する前から諦めたり試すことすらしなくなってしまいますよね。
他にも、私の学生時代の後輩を例に出しましょう。
私もその後輩も吹奏楽部で楽器を吹いていたのですが、
後輩はリズム感に自信がありませんでした。
「私はリズム感がない」と思い込んでしまい、リズムの練習を避けてしまったり、
他の部分でカバーしようとして根本的な問題に向き合えなくなってしまったのです。
結果、上達が遅れてしまったり、苦手意識がさらに強くなることに繋がっていたのではないかと思っています。

思い込みじゃなくて本当のことだったら?
実際に適性や才能がなくて努力しても無理ってパターンもあるよね?

確かにそうだね。
本当に苦手なのか判断するには続けてみないとわからないと思うの。
しばらく続けてみて色んな方法試しても難しい…
そうなったら思い込みじゃなくて本当に苦手なのかもしれない。
でも試行錯誤してくうちに上達していくこともあるから、
取り組む最初の段階で「これは苦手なやつかも」ってなるのは
思い込みの可能性が高いね。

なるほどー!最初から諦めるのは勿体ないよね!
思い込みが行動にブレーキをかけてしまっているかもしれないという可能性を
無視するかしないかはその人次第です。
才能があるかどうかにかかわらず、日々の積み重ねで大きな成果を得られる可能性はあります。
私の後輩も 最終的にリズム感に対する苦手意識を克服し、
そこから演奏技術もみるみる上達していきました。
思い込みにとらわれず、まずは行動してみることが大切です。
2-2.人間関係への思い込みによる影響
思い込みが人間関係に与える影響は、感情面でとても大きなものになります。
特に他人の行動や言葉に対して勝手に「こういう意図だ」と思い込んでしまうと、
本来感じるべき感情とは違うものを抱いてしまうことがあります。
例えば、友人が自分に返事を遅らせた時に「無視されている」「嫌われている」と思い込んでしまうケース。
実際にはただ忙しかったり忘れていただけかもしれませんが、
思い込みが原因でその友人に対して不信感を抱いたり、過度に心配したりしてしまうのです。
このような誤解が積み重なると、自然と距離ができてしまい友情が疎遠になることも。
思い込みによる感情の揺れが良好な関係を崩してしまうことは少なくありません。

思い込みはある意味 人間関係を守るための防御反応でもあるよね?
例えば過去に傷ついた経験がある人なんかは、
同じことを繰り返さないために警戒心や思い込みを持つことで
感情的なダメージを最小限に抑えてるんじゃない?

確かに過去の経験から来る警戒心は自己防衛として必要な場合もあるね。
でもその警戒心が過剰になると、他者の行動に対して過敏に反応してしまって
逆に傷つけられる機会が増えてちゃうの。

そうね…過剰かどうかの見極めが必要よね…
どうすればいいのー!?

それについては共感力が重要になってくるよ!
「3-4.共感力を高める」を参考にしてみてね!

了解です!
2-3.仕事や人生への思い込みによる影響
思い込みは自己評価や将来への期待にも大きな影響を与えます。
特に「自分はこれができない」とか「こういう道しか進めない」といった固定観念が強いと、
可能性を自ら狭めてしまいます。
例えば、ある人が「自分は数学が苦手だからこの分野には進めない」と強く思い込んでいる場合、
その分野に興味があったとしても挑戦することを諦めてしまうことも。
このように自分の限界を思い込みで決めてしまうと、新しいスキルや分野に挑戦する機会を逃してしまい、
長期的に見てキャリアの幅が狭くなってしまいます。

失敗を避けるために無理だと思うことを事前に諦めるのは賢明な判断…
って思う人も多そうね。

確かにリスクを避けるために自分の限界を意識することは必要だけど、
挑戦せずに可能性を見過ごしてしまうのはもったいないと思うな。

うんうん、私もそう思う。
でも仕事なんか特に、失敗したら仕事仲間や顧客に迷惑かかるから
しない方がいいのも事実だよねー。

そうだね。
「失敗を恐る必要がある」場合は、挑戦を諦めるんじゃなくて
「3-3.不確実性を受け入れて思い込みを克服する」の内容を参考にしながら
前向きに考えると良いよ!

はーい!
3.思い込みを克服する心理的方法

次は思い込みから脱却するための方法についてです。
先述の内容で思い込みによって人生の幅を制限している可能性があるということが
分かったのではないかと思います。
ではもっと自由に生きるために、
どうすれば思い込みから脱却できるのかについてですが、
以下4つの方法が良いでしょう。
・自己認識を高め、自問自答しながら思い込みを克服する
・異なる視点を求めて思い込みを克服する
・不確実性を受け入れて思い込みを克服する
・共感力を高める
では早速それぞれ解説していきます。
3-1.自己認識を高め、自問自答しながら思い込みを克服する
思い込みを克服するために、自己認識を高めて自問自答することが有力な方法だといわれています。
これは自分がどのような思い込みにとらわれているのかを意識的に振り返り、
その原因や影響を探る作業です。

実際にどのようにすれば良いのかな?

毎日数分だけでも「その時自分の思考や感情がどこに向いているのか?」を意識する習慣をつけよう!
おすすめはスマホのリマインダーアプリを活用すること。

ほほう!

起きてる時間なら何時でも良いから
毎日「今どこに注意向けてる?」と通知が届くように設定しておく。
その通知を見たらそのタイミングに何に注意を向けているのか意識して、
その意識は「個人的な感情を尊重したもの」なのか
「他の視点も取り入れているものなのか」判断してね!

リマインダー設定しとけば忘れることなくて良いね!
それだけならその場でパッとできそうだし!

うんうん!
ぜひ試してみてね!
ここで個人的な感情を尊重したものだった場合は思い込みの可能性が高いので、
時間があるときに以下の方法で感情と向き合うようにしましょう。
1.「今思い込んでる可能性がある」と自分に言い聞かせる。
例)「職場の上司に怖い」と気づいたら…
「今あの上司が怖いと思い込んでいる」。
2.なぜそのような感情になるのか原因を探る
例)その上司がなぜ怖いのか?
・よくため息をついているから
・よく悪口を言っているから
・質問したら嫌な顔をされるから
3.その感情の根本的な原因は自分自身にあるということを自覚する
例)一見相手の上司が態度悪いのが問題にも思えるけど、
それでも「怖い」と思う根本的な原因は自分自身にある。
なぜなら、このように同じ出来事に遭遇しても人によって捉え方は様々だから。
人によってはこのような上司がいても怖がることなく
「ため息つくと幸せ逃げちゃいますよ」と言いたくなる場合もあるのだろう。
4.別の似た出来事(その感情を抱くようになったきっかけ)を思い出す
例)過去に大好きな親にため息をつかれた経験がショッキングだった。
それがあるから、同じような経験をすると敏感に反応してしまうんだな。
これができるようになったらリマインダーしてない時でも
常に自分を客観的に見てバランスの取れた判断がしやすくなります。
また、日常的に自問自答をすることで自分の考え方の癖に気づき、
不要な思い込みを少しずつ排除していくことができるのです。
この方法は時間をかけて継続することで効果が表れるため、
急に変わらなくても焦らずに取り組むことが大切ですよ。
3-2.異なる視点を求めて思い込みを克服する
思い込みを克服するために異なる視点を求めることが有力だと言われています。
私たちは普段の生活で自分の価値観や経験に基づいて考えがちですが、
異なる視点を取り入れることで自分の思い込みに気づきやすくなるのです。
例えば、ある仕事の進め方に固執しているとします。
「この方法しか成功しない」と思い込んでいる場合、同僚や他業界の人から別のやり方を聞くことで
より効果的な方法を発見できることもあります。

でも全ての意見が自分に合うわけではないし…

そうだね〜
もちろん全てを無理に受け入れる必要はなくて、
ここではまずは異なる視点を取り入れてみるということが大事なの。

そっかー!

その過程で少しでも自分の思い込みに気づけたのなら、それが克服の第一歩。
自分と違う考え方を持つ人と話すだけで、
自分の中にあった固定観念が揺らいだり新たなアイデアが生まれることもあるよ〜!
3-3.不確実性を受け入れて思い込みを克服する
思い込みを克服するための心理的方法として不確実性を受け入れることが有力だという考え方があります。
私たちが何かに思い込む理由の一つは物事を確実に理解したいという気持ちが強いから。
不確実性があると人は不安になり、結果的に自分が信じるものに固執しやすくなります。
ですが、この「全てが確実にわかるわけではない」ということを受け入れることができると、
無理に何かに対して確信を持つ必要がなくなります。
不確実性を許容することで新しい情報や変化に対して柔軟になり、
思い込みに縛られることが減ります。
例えば、将来のキャリアパスに関して。
ある特定の道が自分にとって「正しい選択」だと思い込んでいる人は、
その道以外の選択肢を否定したり失敗を恐れすぎることがあるのですが、
この時に不確実性を受け入れて「他の道もあるかもしれない」と考えると
新しい可能性を探ることができて思い込みにとらわれずに柔軟に動けるようになります。

例えば仕事関係で事前に対策したのにも関わらず、
トラブルが発生して周りに迷惑かけちゃったとしたら?

もちろん、事前に想定できるリスクの対策は大切だよ!
でも対策してもハプニングというのは起こりうること。
そのときには自分を責めすぎず次に活かすための反省をすることで、
結果自分にとっても周りにとっても
「その経験があって良かった」という出来事に変わることが多いので安心してね!

うんうん!
自責と反省は似てるようで全然違うものね!
思い込みにとらわれず、少しずつでも新しいことに挑戦することで
仕事や人生に新しい展望が開けるかもしれませんよ!
3-4.共感力を高める
思い込みを克服するための方法として、共感力を高めることが有力だという考えがあります。
共感力とは、他者の感情や視点を理解しそれに寄り添う力のこと。
思い込みは自分自身の見方や価値観に固執してしまうことから生まれることが多いのですが、
他人の感情や立場に共感できると自分が持っている狭い視野から抜け出しやすくなります。
例えば、誰かが失敗したときに「この人は怠け者だ」と思い込んでしまう場合に、
もしその人の状況や感情に共感できれば
その失敗にはもっと複雑な背景があるかもしれないと気づけます。
「忙しくて準備する時間がなかった」とか「緊張でうまくいかなかったのかも」と、
相手の視点に立って考えることで思い込みから解放されるのです。
また、率直にコミュニケーションを取るように心がけましょう。
相手に対してオープンな態度を持つことでより深い絆を築き、
お互いを理解し合える関係が長続きしやすくなりますよ。

共感力を高めることは感情に流されやすくならない?

人によっては流されちゃうかもだけど…
そもそも共感力を高めることは感情的になることとは違うから
それを知った上でもし感情的になったら「3-1.自己認識を高め、自問自答しながら思い込みを克服する」の感情と向き合う方法を試してみてね!

はーい!
他者の立場を理解しようとすることで、
最終的には多角的な視点で冷静に判断する力を養うことができます。
自分の思い込みを和らげ、バランスの取れた視野を持つための重要なステップになるのです。
4.まとめ
いかがだったでしょうか?
簡単におさらいをしましょう。
・思い込みは主に「ステレオタイプ」「バイアス」「防衛機制」「選択的注意」
「社会的影響」から起こる
・「苦手」という意識が思い込みなのかを判断するにはまず続けてみて試行錯誤すること
・「人間関係への思い込み」は過剰にならないように注意
・「失敗を恐れるが故の思い込み」で可能性を見過ごさないように注意
・スマホのリマインダーアプリを活用して「その時自分の思考や感情がどこに向いているのか?」を意識するよう身につける
・あえて周囲の異なる情報を取り入れると固定概念が変わる可能性も
・「全てが確実にわかるわけではない」と思えると思い込みに縛られにくい
・「共感力」を高めることで人間関係が良好に
今回は思い込みが起こる人間の心理、行動や判断・人間関係・仕事や人生に与える影響、
克服方法についてまとめてみました。
自分自身を冷静に見つめ、周囲とのつながりを大切にしながら柔軟な思考を持つことが、
より豊かな人生への第一歩です。
SNSでも心理学に関する内容や前向きな考え方等について公開しています!
フォロー等していただけると今後の活動の励みになりますので、
もし宜しければお願いいたします…!
各SNS(TikTok、X、Instagram)
REALITYで配信中!


最後まで読んでいただきありがとうございました!
あなたに幸あれ!
またねです〜!



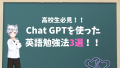
コメント